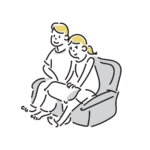ジェロントロジーに関する耳寄りな情報 第114回(ジェロ・マガ Vol.114[2025年9月16日]より一部抜粋)
このコーナーでは、ジェロントロジーに関連する、日々の生活や今後の生き方に役に立つ、あるいは「耳寄りな」情報をお届けいたします。
—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-
今回は、「認知症」について話題提供いたします。
●毎年9月は「世界アルツハイマー月間(認知症月間)」、9月21日は「世界アルツハイマーデー(認知症の日)」
1994年に国際アルツハイマー病協会(ADI)が定めたこの月間、日は、認知症への理解と関心を深めるための世界的な取組です。日本でも2024年に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、9月21日が「認知症の日」、9月が「認知症月間」と正式に位置づけられました(※1)。
※1 政府広報オンライン「認知症月間」
●認知症とともにある日々
身近に認知症や介護を必要としている人がいないと、その日常の揺らぎや、静かな葛藤に気づきにくいことも考えられます。でも、すでにその現実の中にいる人たちは、「病気」や「制度」だけでは語りきれない、関係性の変化や感情の波に、日々向き合っています。怒りや戸惑い、悲しみ、心身と金銭的な負担の大きさ、いつまで続くのかわからないことへの不安、状況を理解してもらえなかったり、代わってもらえないことへの失望、関係性を重ねてきたからこその思い出や以前とは関係性が変わったことで新たに気づいたこと──それらはすべて、認知症とともにある暮らしの一部であり、毎日の現実です。だからこそ、物語や経験の言葉に触れることで、まだその現実にいない人も、「自分には関係ない」と思っていた人も、少しずつ、認知症を「自分の暮らしや社会の中のこと」「自分とも関係のあること」として受け止めるきっかけになるのだと思います。
そして、その気づきは、「どう受け止めるか」「どう関わるか」「どう支えるか」「どう共に生きるか」を考える入口になり、社会の一員として、自分にもできることを見つけていく力になるのではないでしょうか。なぜなら、人生100年時代を生きる私たちにとって、判断能力が不十分な状態になることは、誰にでも起こりうる身近な問題であって、一人一人が当事者であると考えられるからです。
●本人や家族、社会との関係性、関わり方を知る書籍や映画等
認知症にまつわる感情や周囲の人との関係性の変化、その向き合い方のヒントを得るには、物語の力も大きな助けになります。例えば、『マンガ ぼけ日和』(矢部 太郎、2023年)は、認知症専門医である長谷川嘉哉先生原案の書籍を、お笑い芸人である矢部太郎さんが漫画化されたものです。この本では、「老い」「認知症」「介護」「死」を、誰にでも訪れるあたりまえのこととして描きながら、読者の不安をやわらげてくれます。漫画を描いた矢部さんは、少しでも症状について知っておくと、実際にその状況になったとしても心構えや不安をやわらげ、少しでも備えられるとおっしゃっています。矢部さんは、長谷川先生から聞いて印象に残ったエピソードとして、認知症のお年寄りが、身近な家族に対して「お金を盗った」と怒り出すことがあるが、それは「あなたがいないと困る」という気持ちと関係性の表現であり、最も頼りにしている人に向けて発せられる言葉なのだ、というお話を挙げています。長谷川先生は、講演を聞いた方から「そのことを早く知っていれば、少しは受け入れられたかもしれない」と言われて、本を書こうと思ったとおっしゃられていたということです(※2)。
※2 yomiDr.「[矢部太郎さん](下)認知症患者と家族の日常を描いた「マンガ ぼけ日和」 介護する人の不安をとりのぞいてくれるものとは?」2024年7月14日
また、映画『明日の記憶』(2006年)は、広告代理店で営業部長として働く男性が、働き盛りの50歳を目前に、若年性アルツハイマー病と診断される作品です。この作品は、認知症が高齢者だけの課題ではなく、現役世代にも起こりうる病気であることを伝えています。「今を生きることの尊さ」「自分の存在が誰かの記憶の中で生き続ける希望」だけでなく、会社や社会がどう受け止め、支えるかを私たちに問いかける映画でもあります。こうした物語に触れることで、認知症は「誰かの問題」ではなく、「私たちの暮らし、私たちの社会にとっての自分事」として位置付けることができます。
●認知症とともに暮らす社会へ──私たちにできること
私たちは、物語や、身近な自治体、企業の取組等を通じて、認知症という症状とともに、そもそも「その人(自分を含む)」に目を向けることの大切さに気づかされます。「その人(自分を含む)」の周囲の人とのそれまでの関係性、誰にでも、大事にしてきたもの、できること、苦手なこと、困っていること、以前はできていたことができなくなって悲しいと感じていること等があり、そして、自分も周りもどのように心構えをして、対応していくか――そうしたことを、改めて見つめ直す機会にもなります。そしてその見つめ直しは、自分自身の生き方や人とのつながり、「自分や家族が、社会の誰でもが安心できる社会をつくること」や、「社会の一員として自分にもできること」を考えるきっかけにもなると思います。
最近は、多くの自治体で「認知症カフェ」や「本人ミーティング」等の取組が重ねられています(※3)。また、誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて、モノづくりやサービスを検討する過程で「当事者参画型開発」を行う企業も増えています(※4)。
※3 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター「本人の声を起点とした認知症地域支援体制づくりガイド」2018年3月
※4 経済産業省「「認知症当事者とともにつくる」先行事例紹介」
そして、9月21日は「認知症の日(世界アルツハイマーデー)」として、特に啓発活動が強化され、オレンジ色のライトアップなども行われます。書籍や映画、お住まいの地域の自治体等のウェブサイト等をご覧いただくと、ご関心のある情報を発見できるかもしれません。9月という節目に、認知症とともにある暮らしや社会に目を向けてみませんか。