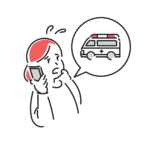ジェロントロジーに関する耳寄りな情報 第116回(ジェロ・マガ Vol.116[2025年10月14日]より一部抜粋)
このコーナーでは、ジェロントロジーに関連する、日々の生活や今後の生き方に役に立つ、あるいは「耳寄りな」情報をお届けいたします。
—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-+—-
プラス面としてのランニングの効果については、以前のジェロ・マガ(Vol.94)でお伝えしたところですが、マイナス面としてマラソン大会中に心肺停止状態になるランナーがいることもまた事実です。実際に私が参加したマラソン大会でも、そのような現場に遭遇した経験もあります。慶應義塾大学スポーツ医学研究センター他の研究グループ報告※1によると、2011年4月〜2019年3月に実施された日本陸連公認コースでのマラソン大会(516大会、のべ参加者約410万人)のうち、69例(男性66例・女性3例)の心肺停止が発生し、68例が救命されたそうです(救命率98.6%)。参加者10万人あたりの心停止発生率は1.7%で、傾向的には特に60歳以上の男性は注意する必要性が示唆されているとのことです。
※1:プレスリリース「日本陸連公認コースマラソン大会における年齢層別心停止発生状況を調査」
東京マラソン財団の情報※2によると、日本最大のマラソン大会である東京マラソン過去16回(2007〜2023年)の開催(のべ参加者約51.9万人)のうち、11名のランナーが心肺停止に陥ったそうです。ただ、周りのランナーやボランティア、救護スタッフの迅速な救命活動のお陰で救命率100%を達成しているそうです。
※2:東京マラソン財団「救命救急情報」
これまではスポーツ中の心肺停止を見てきましたが、これから本格的に寒くなってくると入浴中の心肺停止(寒暖差による血圧の急激な変動、熱いお湯に長時間つかることによる血圧低下・水分喪失等)にも注意が必要です。このように考えるとスポーツ中に限らず、普段の生活でも起こり得る可能性があり、逆に他の方の心肺停止の場面に遭遇する可能性も否定できません。そうなって来ると、心肺停止直後の応急手当が生死を分けるとされています。心肺停止になってから救命処置が行われるまでの時間経過と救命率との関係(救命曲線)によると、心肺停止から1分以内では95%ですが、3分以内では75%に低減し、5分経過すると25%、8分経過すると救命可能性は極めて低くなります。救急隊が現場到着までに平均約7.7分、通報から救急救命士による救命処置開始までが平均12分とのことですので、現場に居合わせた人(バイスタンダー)による迅速な応急手当が生死を分けることが理解できると思います。※3
※3:八王子整形外科「救命処置」
バイスタンダーによる応急手当の方法や留意点等を分かりやすく体験・学習するためには、日本各地の消防局・消防本部が実施している救命講習※4、日本赤十字社の赤十字救急法基礎講習※5などがお勧めです。私も最近オフィス近隣の消防署で救命講習を受講する機会がありましたが、胸骨圧迫の大変さやAEDの使用方法等を実際に体験でき、とても有意義でした。
※4:東京消防庁「応急手当講習会 救命講習のご案内」
※5:日本赤十字社「救急法」
皆さんのご家族や大切な方に万一のことがあった時や偶然そうした場面に遭遇した時、バイスタンダーによる応急手当で救える命があることを、自身を含めて忘れずにいたいと思います。